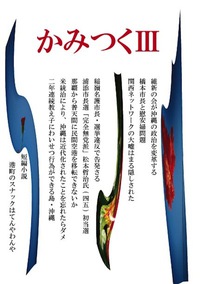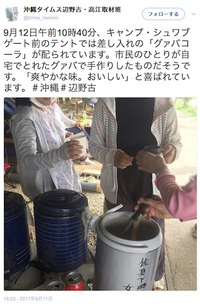2013年08月16日
1963年8月17日みどり丸遭難事故と米軍の救援活動
2013年8月5日、宜野座で嘉手納基地第三十三救難中隊所属のHH60救難ヘリが墜落、マーク・A・スミス三等曹長(30)が殉職されたほか3名が怪我をされた。
マーク・A・スミス三等曹長のご冥福とご遺族に謹んで哀悼の意を表したいと思います。また、怪我をされた3名の方々が早く回復される事を願います。
9年前、沖国大に普天間基地のヘリコプターが墜落した事、また普天間基地所属のCH-46ヘリコプターの代替としてMV-22オスプレイが飛来している事でエスカレートする反米活動にとっては格好のネタとなっている。(マスコミは「追加配備」と報道しているがMV-22の数だけを数えると増えている様に見えるが実際にはCH-46という老朽化した機種が退役しているので「追加配備」という表現は事実を誤認させる表現である様に思われます。)
実際に野嵩ゲート前、平日限定で早朝集結し反米活動を行っている団体は「海兵隊のヘリが墜落しパイロットが死にました。(海兵隊というのは彼らの事実誤認)小学校に近い所であり小学校に落ちたら誰が責任を取るんでしょうか。」と叫んでいる。似非平和団体はヘリが墜落しスミス三等曹長が亡くなった事を喜んでいる(そんな事はないと思いますが)ような印象を受けます。確かに、航空機が墜落するというのは大変な事ですが、飛んでいるものが絶対に落ちないという事もありえないことです。上空へ飛んで行った風船ですらいつかは落ちてきます。空を飛ぶ鳥も落ちます。蝉が路上に落ちているのは夏の風物詩でもあるかもしれません。
基地周辺で風船や凧揚げをする事がどれだけ危険な事か、ヘリ墜落を糾弾する方々が理解できないはずがありません。8月8日、民間機と鳥の衝突で那覇空港発着のダイヤが乱れました。仲井眞知事が東京から戻る便も影響を受けましたので知事もご存知でしょう。
「みどり丸遭難事故」をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。1963年8月17日(明日で丁度50年になります)、泊港から久米島へ向け出港した客船が神山島沖で沈没した事故です。
乗客194人、乗員14人に加えて乗客名簿に記載されていない人が40人程いたとみられています。
86人が亡くなり、行方不明者は26人といわれています。
みどり丸は午前11時5分出港、正午過ぎに高波(三角波?)をうけSOSを発信する暇もなく転覆したとみられます。
漂流していた二人が近くを航行する砂利運搬船「慶福丸」に発見されましたが運の悪い事に「慶福丸」には無線がなく、泊港へ急行した。事故が報告されたのは約4時間経過した午後4時過ぎとなってしまった。
事故の発生は各所へ伝えられ、沖縄タイムスは午後5時前に警察担当記者から「みどり丸遭難」とデスクに急報が入り、那覇港から4トンの小型船「長島丸」をチャーターし午後5時半頃には那覇港を出港し現場へ急行した。
取材に出かけた訳ではあるが沖縄タイムスの又吉稔氏、写真部の池宮城氏、RBCカメラマン末吉氏らは海上に放り出された多くの遭難者が救いの手を求めて波間に浮いている現状を目の当たりにして取材者から救助者となった。沖縄タイムスがチャーターした「長島丸」は午後7時から8時の間に神山島付近で33人(うち女子5人)を救助している。
現場は午後6時半頃から次第に暗くなり(50年前の今なので夕暮れ時は同じですね)ヘリコプターから落とす照明弾の光を頼りに救助活動を継続、ヘリコプターは遭難者を宙づりで救助船や近くの島へ運び、重傷者は那覇空港へ運び那覇病院、那覇空軍付属病院などへ収容された。
米軍の活動の様子はどうだったのか?当時の新聞報道をみてみましょう。
(8月19日沖縄タイムス)
(8月23日 琉球新報)
「みどり丸」沈没 1963年8月18日朝刊
琉球新報アーカイブより
久米島定期船「みどり丸」転覆
毎日新聞報道(毎日jpより)
また、同日にはみどり丸沈没の他、藤田航空機八丈富士墜落事故wikiも起こっている。藤田航空機事故では自衛隊と在日米軍が捜索活動を行っています。wikiも併せてご覧ください。
復帰前の当時、自衛隊の存在しなかった沖縄ではこのような非常事態に置いて米軍の機動力というものがこれほど役に立ったのである。沖縄タイムスも琉球新報も報道記事から感謝の気持ちが読み取れる。
また、取材に向かったはずの沖縄タイムスも救いの手を求める遭難者を目の前にして傍観者ではいられず、一所懸命救助活動をしていた様子がうかがえる。
マスコミ人であるまえに人間として行動したのであろう。当然といえば当然なのかもしれないが賞賛される事はあっても非難する人はいないだろう。
今の沖縄のマスコミ関係者にも同じ事が期待できるだろうか。いや、マスコミだけでなく議会、識者、一般人でもだ。
目の前で苦しがっている人がいたら、たとえ自分に救う力や知識がなくても
なんとかしたいと思う気持ちがでないだろうか。
そこで、誰かが手を差し伸べて苦しんでいる人を救ってくれたら苦しんでいる人が誰であっても、救助者が誰であってもあたたかい拍手を贈りたくはならないだろうか。救助活動をおこなったにもかかわらず残念な結果になったとしても誰も責める事はできないのではないだろうか。
勘のいい方は気がついたかもしれないが、8月5日に墜落したHH60型救難ヘリは第三十三救難中隊所属で50年前にみどり丸遭難事故で最も活躍した部隊なのである。
ヘリコプターが墜落してしまった事は残念であるが、はじめにも書いた様に飛行機はおろか鳥や昆虫、風船やタコなど空を飛ぶもので絶対に落ちないものなどこの世に無いわけで、議会や政治家、マスコミ等は抗議する前に亡くなったマーク・A・スミス三等曹長に哀悼の意を表し、遺族や怪我をされた3人の隊員に対して安らぎのメッセージを贈るべきではないだろうか。

明日はみどり丸遭難事故と藤田航空機八丈富士墜落事故から50年になります。
海と空で亡くなった方々のご冥福をお祈りすると同時に
非常時に備えて日夜努力されている米軍、自衛隊の方々に改めて敬意を表していただければ幸いです。
<つづく>
『沖縄に内なる民主主義はあるか』定価:1735円(税・送料込み)
季刊誌「かみつく」創刊号紹介HP
価格 1420円(税・送料込み)
「かみつく�」定価:1735円(税・送料込み)
ネットから御注文を受け付けています。
ezaki0222@ybb.ne.jp
※↑↑こちらまで住所氏名と電話番号を御連絡いただければ、受注当日か翌日までに発送いたします
<送金方法等詳細はここ>
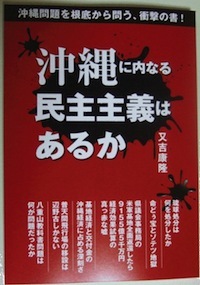
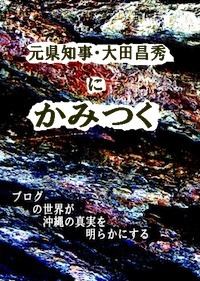
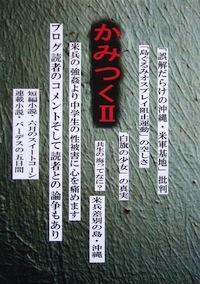
「かみつく� 」の目次
「かみつく」の内容紹介
「沖縄に内なる民主主義はあるか」の内容紹介
マーク・A・スミス三等曹長のご冥福とご遺族に謹んで哀悼の意を表したいと思います。また、怪我をされた3名の方々が早く回復される事を願います。
9年前、沖国大に普天間基地のヘリコプターが墜落した事、また普天間基地所属のCH-46ヘリコプターの代替としてMV-22オスプレイが飛来している事でエスカレートする反米活動にとっては格好のネタとなっている。(マスコミは「追加配備」と報道しているがMV-22の数だけを数えると増えている様に見えるが実際にはCH-46という老朽化した機種が退役しているので「追加配備」という表現は事実を誤認させる表現である様に思われます。)
実際に野嵩ゲート前、平日限定で早朝集結し反米活動を行っている団体は「海兵隊のヘリが墜落しパイロットが死にました。(海兵隊というのは彼らの事実誤認)小学校に近い所であり小学校に落ちたら誰が責任を取るんでしょうか。」と叫んでいる。似非平和団体はヘリが墜落しスミス三等曹長が亡くなった事を喜んでいる(そんな事はないと思いますが)ような印象を受けます。確かに、航空機が墜落するというのは大変な事ですが、飛んでいるものが絶対に落ちないという事もありえないことです。上空へ飛んで行った風船ですらいつかは落ちてきます。空を飛ぶ鳥も落ちます。蝉が路上に落ちているのは夏の風物詩でもあるかもしれません。
基地周辺で風船や凧揚げをする事がどれだけ危険な事か、ヘリ墜落を糾弾する方々が理解できないはずがありません。8月8日、民間機と鳥の衝突で那覇空港発着のダイヤが乱れました。仲井眞知事が東京から戻る便も影響を受けましたので知事もご存知でしょう。
「みどり丸遭難事故」をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。1963年8月17日(明日で丁度50年になります)、泊港から久米島へ向け出港した客船が神山島沖で沈没した事故です。
乗客194人、乗員14人に加えて乗客名簿に記載されていない人が40人程いたとみられています。
86人が亡くなり、行方不明者は26人といわれています。
みどり丸は午前11時5分出港、正午過ぎに高波(三角波?)をうけSOSを発信する暇もなく転覆したとみられます。
漂流していた二人が近くを航行する砂利運搬船「慶福丸」に発見されましたが運の悪い事に「慶福丸」には無線がなく、泊港へ急行した。事故が報告されたのは約4時間経過した午後4時過ぎとなってしまった。
事故の発生は各所へ伝えられ、沖縄タイムスは午後5時前に警察担当記者から「みどり丸遭難」とデスクに急報が入り、那覇港から4トンの小型船「長島丸」をチャーターし午後5時半頃には那覇港を出港し現場へ急行した。
取材に出かけた訳ではあるが沖縄タイムスの又吉稔氏、写真部の池宮城氏、RBCカメラマン末吉氏らは海上に放り出された多くの遭難者が救いの手を求めて波間に浮いている現状を目の当たりにして取材者から救助者となった。沖縄タイムスがチャーターした「長島丸」は午後7時から8時の間に神山島付近で33人(うち女子5人)を救助している。
現場は午後6時半頃から次第に暗くなり(50年前の今なので夕暮れ時は同じですね)ヘリコプターから落とす照明弾の光を頼りに救助活動を継続、ヘリコプターは遭難者を宙づりで救助船や近くの島へ運び、重傷者は那覇空港へ運び那覇病院、那覇空軍付属病院などへ収容された。
米軍の活動の様子はどうだったのか?当時の新聞報道をみてみましょう。
(8月19日沖縄タイムス)
みどり丸の救助活動に米軍は大きく活躍した。とくに那覇基地第三十三航空救助隊はその機動力と職業的活動力を発揮、琉米救助班のスムーズな活動が大きな海難事故にもかかわらず数多くの遭難者の救出を成功に導いた。
この救助作業に直接あたってきた那覇基地第三三航空救助隊指揮官R.P.アシュ大佐、航空救助コントロール・センター調整官H.ワンドーフ少佐、HU16型水上機パイロットD.A.マクガイア大尉、SU16型救助機乗組員J.W.アダムス少尉らとインタビュー、事故の模様をきいてみた。次は一問一答の要旨。
事故の連絡と救助の要請をうけたのは何時頃か。
「アシュ指揮官」十七日午後五時二十分頃“砂島”の沖合で小型船が転覆したらしいとの連絡が民政府公安部からあり、直ちに救助の要請があった。救助隊は五時四十五分HU16型水上機を現場の確認と呼び捜索に派遣、同機から“確認”の無電があったので常駐救助班が出動、同時に航空救助コントロール・センターを通じ陸海、空、海軍、マリン隊に連絡、ヘリコプター十三機、救助機三機が出動した。
最初に救助したのは。
「マクガイア大尉」水上機は遭難地域を捜索飛行、ヘリコプターで救助作業をやった。最初はヘリから綱を降ろして掴まった人たちを一人ひとり引き上げ、砂島へ救出した。
現場はどうだったか。
「答え」あちこちに点々とグループになって船のベンチや積んでいたらしい材木につかまって浮いていた。母親が子供を求めて呼んでいる声もきかれた。綱を降ろしても掴まれない人もいた。
救助のあとに基地に運ぶ途中死んだものもあった。
「アダムス少尉」十七日作業のときは約七マイル四方の範囲にあちこちに船から流れたらしいベンチや木材などに掴まっては波間に浮いていた。十八日も捜索にあたったが遺留品が海に浮いているだけで人は発見できなかった。
救助地域はどうなっているか。
「マ大尉」現場を中心に東西南北に約十二マイル四方を十五ノットの速度で各機が七十五ヤードの間隔で三百フィートの上空を網目をつくるように捜索する、陸軍機は西海岸に沿って捜索した。
今後の捜索は。
「ア指揮官」十九日も捜索を続ける。まだ発見できる可能性がある。個人差はなるが現在の海上の状態なら一週間は漂流しても生きている。
(8月23日 琉球新報)
「ナウ・ヒーヤ・ジス、第三十三救助中隊全員、直ちに部署につけ、緊急命令!」週末の十七日那覇飛行場全域を結ぶラウド・スピーカーが、将校クラブ、下士官クラブ、航空兵クラブでいっせいにこの非常命令を伝えた。スワッとばかりに全要員が飛び出した。
水泳着姿のもの、アロハシャツの将校、ハダカの兵隊。しかしこうして魔の十七日は沖縄海域史上最大の事故といわれる「みどり丸遭難事件」は最小限にその犠牲を食い止める事ができた。そしてそれは「人命に関するかぎりウワサでも飛行機を飛ばせ」と命ずる米軍の徹底したヒューマニズムと緻密な活動に追う所が大きかったといえよう。
みどり丸遭難事故では、米陸、海、空、マリンの四軍が一体となって救助、捜索に当たった。
遭難事故の第一報は米陸軍司令部から那覇航空隊内のADCC(防空管制センター)に報告されADCCから同時に全軍に通報された。
こうして陸海空、マリンのヘリコプターや水陸両用機、軍船の出動による救助活動となったが、中でも目ざましい活動をしたのが、人命救助を使命とする那覇基地の第五十一航空隊付属三十三救助中隊(隊長:ロバートP・アッシ中佐)。
ADCCから救助中隊内にあるRCC(救助コントロール・センター)に第一報が入ったのが午後五時四十五分。白ズボンの海辺着をつけていた中佐はそのままの姿で指揮官室にとび込んで来た。
その時までの情報は「沖縄の漁船がそうなんしたというウワサがある」というものだった。アッシ隊長は「人命に関する限り“ウワサだから”ではすまされぬ。無駄でもいいから飛行機を飛ばすんだ。」と命令、ブザーが鳴り、将校、下士官、兵の各クラブで拡声器が非常呼集を伝えた。
第三十三救助中隊はHU型大型水陸両用機七機とHU19型ヘリコプター二機兵員百四十からなり、そのうち大型水陸両用機一機とヘリ一機は常時配置についている。その救助作業分担区域は沖縄から南は遠くシンガポール、サイゴン方面まで及んでいる。
緊急指令と同時に中隊作戦次長のヘンリ・ウォーレンドーフ少佐が飛行機に乗って指揮をとった。水陸両用機から照明弾を約七百メートル間隔で長さ八キロの照明範囲で投下、海面を照らす一方、ヘリコプターはフック(救助用カギ)や救命帯などで救い上げ、また海上捜査の便宜をはかった。使用した照明弾は二百個以上。これを補給するためにヘリコプターは八回も基地を往復、また同中隊だけでも延べ十五機が作業に従事したという。
その晩は将校も、下士官も兵も司令部内にサンドウィッチを運びイスを並べてゴロ寝した。
「みどり丸」遭難事故、それは第三十三救助中隊にとっても近年にない作戦を展開させるほどの事故であった。
無口なアッシ中佐は今度の遭難事故について「多くの人命が失われた事が遺憾でならない」とのべ言葉少なに次の様に語っている。
「アッシ中佐の話」われわれは人命を助けるのが使命であり、搭乗員は危険にも耐え得るように訓練されている。単なるウワサでも、こと人命に関する限り飛行機を飛ばす事はムダな事ではない。今度の場合、多くの人命が失われた事が遺憾でならない。
「みどり丸」沈没 1963年8月18日朝刊
琉球新報アーカイブより
久米島定期船「みどり丸」転覆
毎日新聞報道(毎日jpより)
また、同日にはみどり丸沈没の他、藤田航空機八丈富士墜落事故wikiも起こっている。藤田航空機事故では自衛隊と在日米軍が捜索活動を行っています。wikiも併せてご覧ください。
復帰前の当時、自衛隊の存在しなかった沖縄ではこのような非常事態に置いて米軍の機動力というものがこれほど役に立ったのである。沖縄タイムスも琉球新報も報道記事から感謝の気持ちが読み取れる。
また、取材に向かったはずの沖縄タイムスも救いの手を求める遭難者を目の前にして傍観者ではいられず、一所懸命救助活動をしていた様子がうかがえる。
マスコミ人であるまえに人間として行動したのであろう。当然といえば当然なのかもしれないが賞賛される事はあっても非難する人はいないだろう。
今の沖縄のマスコミ関係者にも同じ事が期待できるだろうか。いや、マスコミだけでなく議会、識者、一般人でもだ。
目の前で苦しがっている人がいたら、たとえ自分に救う力や知識がなくても
なんとかしたいと思う気持ちがでないだろうか。
そこで、誰かが手を差し伸べて苦しんでいる人を救ってくれたら苦しんでいる人が誰であっても、救助者が誰であってもあたたかい拍手を贈りたくはならないだろうか。救助活動をおこなったにもかかわらず残念な結果になったとしても誰も責める事はできないのではないだろうか。
勘のいい方は気がついたかもしれないが、8月5日に墜落したHH60型救難ヘリは第三十三救難中隊所属で50年前にみどり丸遭難事故で最も活躍した部隊なのである。
ヘリコプターが墜落してしまった事は残念であるが、はじめにも書いた様に飛行機はおろか鳥や昆虫、風船やタコなど空を飛ぶもので絶対に落ちないものなどこの世に無いわけで、議会や政治家、マスコミ等は抗議する前に亡くなったマーク・A・スミス三等曹長に哀悼の意を表し、遺族や怪我をされた3人の隊員に対して安らぎのメッセージを贈るべきではないだろうか。

明日はみどり丸遭難事故と藤田航空機八丈富士墜落事故から50年になります。
海と空で亡くなった方々のご冥福をお祈りすると同時に
非常時に備えて日夜努力されている米軍、自衛隊の方々に改めて敬意を表していただければ幸いです。
<つづく>
『沖縄に内なる民主主義はあるか』定価:1735円(税・送料込み)
季刊誌「かみつく」創刊号紹介HP
価格 1420円(税・送料込み)
「かみつく�」定価:1735円(税・送料込み)
ネットから御注文を受け付けています。
ezaki0222@ybb.ne.jp
※↑↑こちらまで住所氏名と電話番号を御連絡いただければ、受注当日か翌日までに発送いたします
<送金方法等詳細はここ>
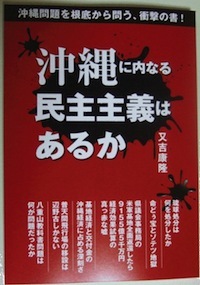
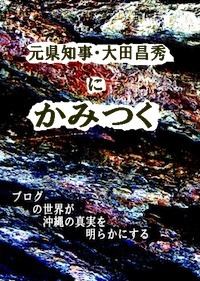
「かみつく� 」の目次
「かみつく」の内容紹介
「沖縄に内なる民主主義はあるか」の内容紹介
Posted by ヒロシ@tida at 01:07